本町公民館(ほんちょうこうみんかん)
更新日:2025年7月31日
施設概要
施設はありませんが、中央公民館を主な活動場所としています。
対象区域
本町1・2丁目、仲町、星川1・2丁目、鎌倉町、弥生1・2丁目、宮町1・2丁目、末広1から3丁目、筑波1から3丁目、銀座1から7丁目、箱田1から7丁目、桜木町1・2丁目、万平町1・2丁目、曙町1から5丁目、肥塚、肥塚1から4丁目、中西1から4丁目、中央1・2・4丁目の全部
末広4丁目、箱田、河原町2丁目、宮前町2丁目、上之、上川上、平戸、戸出、円光1丁目、円光2丁目、中央3丁目、中央5丁目の各一部
(注釈)熊谷東、熊谷西、桜木の3つの小学校の通学区域全体
「本町」地域について
札の辻跡(ふだのつじあと)

札の辻跡
札の
熊谷宿の
場所については、「町往還中程に建置申候」と記され、木柵で囲まれた屋根のある
熊谷市指定記念物史跡。
本陣跡(ほんじんあと)

本陣跡
江戸時代、各街道の宿場町に置かれた大名や幕府役人・公家・貴族などのための特別な旅館です。熊谷宿には竹井本陣・
熊谷市指定記念物史跡。
陣屋跡(じんやあと)

陣屋跡
江戸時代、熊谷宿は
熊谷市指定記念物史跡。
戦災者慰霊の女神像
戦災者慰霊の女神像
1975年に、星川に建てられた戦災者
星溪園(せいけいえん)

星溪園庭園
竹井
この池は元和9年(1623)、荒川の洪水により当園の西方にあった土手(北条堤)が切れてできたもので、その池には清らかな水が湧き出るので、「玉の池」と呼ばれ、この湧き水が星川の源となりました。昭和初期、この地を訪れた前大徳牧宗禅師(ぜんだいとくぼくしゅうぜんじ:大徳寺僧:京都臨済宗)が、「
熊谷新八景『石上寺櫻堤』
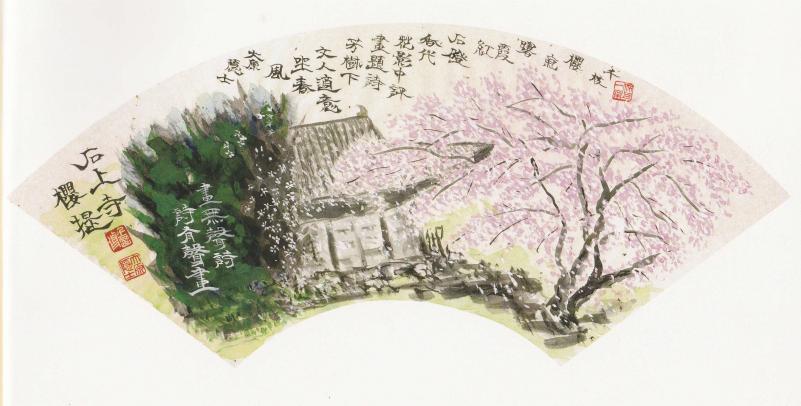
熊谷桜が咲き誇る花の御寺を詠んだもの。
石上寺櫻堤
千枝櫻気曙霞紅
石燈香台花影中
評画題詩芳樹下
文人適意坐春風
(大意)
枝々には桜の気が
石段の上にある御寺は、花影の中に見え隠れする
画を評し、詩を論ずる桜の木のもと
文人は正に真意を得て、春風に座している

