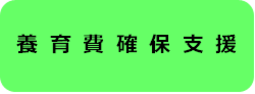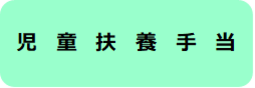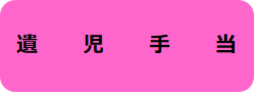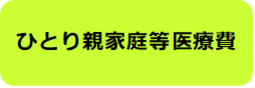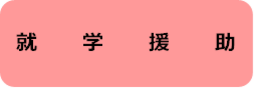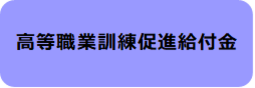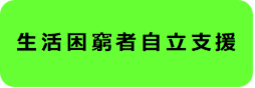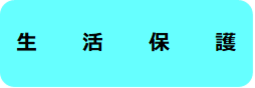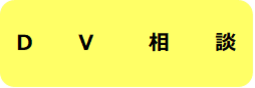手続も、情報も。あなたの”今”に寄り添うワンストップサービス
このページは、ひとり親家庭のかたを対象とした各種支援制度をまとめた情報サイトです。
対象となる手続は、このページからオンラインで申請できます。
「どの制度が使えるのか知りたい」「申請はどこから?」というかたは、ぜひご活用ください。
各制度の詳細は、下記ボタンをクリックしてご確認ください。
|
【離婚前・別居中のかた】
|
| 離婚前や別居中でも養育費の支援が受けられます。早めの相談が将来の安心につながります。 |
| (対応制度)養育費確保支援制度 |
|
【手当・貸付を希望するかた 】
|
| 日々の生活を支えるための現金給付や、必要に応じた貸付制度など、経済的負担を軽減するしくみがあります。 |
| (対応制度)児童扶養手当・遺児手当・母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
|
【医療費の負担が心配なかた】
|
| お子さまと保護者の医療費負担を軽くできる制度があります。通院や治療にかかる費用の心配を和らげます。 |
| (対応制度)ひとり親家庭等医療費 |
|
【教育・学費の支援を探しているかた】
|
| お子さまの学用品や給食費など、学校生活にかかる費用を支援する制度があります。 |
| (対応制度)就学援助制度 |
|
【就職・資格取得を考えているかた 】
|
| 将来の安定した就職やキャリアアップに向けて、生活費や学費の支援が受けられる制度があります。 |
| (対応制度)高等職業訓練促進給付金・自立支援教育訓練給付金 |
|
【緊急時の支援を必要としているかた】
|
| 経済的困窮や家庭内暴力で安心できないかたの生活再建や避難を支援する制度があります。 |
| (対応制度)生活困窮者自立支援制度・生活保護・DV相談 |
養育費確保支援制度
| 対象者 |
熊谷市在住で20歳未満の児童を扶養するひとり親、または離婚協議中で扶養予定のかた |
| 支援内容 |
養育費の取決めに係る公正証書など作成費用、養育費保証契約締結費用を補助します。 |
| 申請方法 |
電子申請・窓口申請(こども課) |
児童扶養手当
| 対象者 |
父母の離婚や死別などで父または母と生計を同じくしていない18歳までの児童(障害がある場合は20歳未満)を養育するかた |
| 支援内容 |
ひとり親家庭の生活安定と自立促進のため、児童の人数や所得に応じた手当を支給します。 |
| 申請方法 |
電子申請・窓口申請(こども課) |
ひとり親家庭等医療費助成
| 対象者 |
熊谷市在住で医療保険に加入しているひとり親家庭などの18歳年度末までの児童とその母(父)または養育者(一定の障害がある児童は20歳未満まで) |
| 支援内容 |
医療機関での保険診療の一部負担金(自己負担分)を助成します。自己負担額があります。 |
| 申請方法 |
電子申請・窓口申請(こども課) |
遺児手当
| 対象者 |
両親または父母のいずれかを亡くされた義務教育修了前の児童を養育している熊谷市在住の保護者で、世帯所得が生活保護基準の1.5倍以下の世帯 |
| 支援内容 |
対象児童1人につき月額3,000円を支給します。所得制限があります。 |
| 申請方法 |
電子申請・窓口申請(こども課) |
高等職業訓練促進給付金
| 対象者 |
児童扶養手当受給者または同等の所得水準にあるひとり親の母または父で、対象資格の取得を目指し6か月以上の養成機関に修業するかた |
| 支援内容 |
修業期間中、生活費として非課税世帯は月10万円(修了前12か月間は14万円)、課税世帯は月7.05万円(同11.05万円)が支給され、修了後には非課税世帯5万円・課税世帯2.5万円が一回限りで支給されます。 |
| 申請方法 |
電子申請・窓口申請(こども課) |
自立支援教育訓練給付金
| 対象者 |
熊谷市在住で20歳未満の子どもを育てるひとり親で、就職のため教育訓練が必要と認められるかた |
| 支援内容 |
入学金、受講料などの費用の一部を補助。講座の種類によって補助率が異なります。 |
| 申請方法 |
電子申請・窓口申請(こども課) |
母子父子寡婦福祉資金貸付金
| 対象者 |
母子家庭の母、父子家庭の父(原則として生計中心者、20歳未満の子を扶養)、父母のない20歳未満の子、寡婦、特定の離婚などで配偶者のない40歳以上の女性 |
| 支援内容 |
就学支度資金、修学資金、就職支度資金、生活資金、転宅資金など、無利子または低利で資金を貸し付けます。 |
| 申請方法 |
窓口申請(こども課) |
就学援助制度
| 対象者 |
小・中学校に就学する児童・生徒がいるご家庭で、経済的にお困りの世帯(児童扶養手当受給世帯、市民税非課税世帯、生活保護に準ずる世帯など) |
| 支援内容 |
新入学用品費、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、オンライン学習通信費、学校給食費、林間学校給食費、特定の疾病にかかる医療費など、就学費用の一部を援助します。 |
| 申請方法 |
学校経由・窓口申請(教育総務課) |
生活困窮者自立支援制度
| 対象者 |
仕事や生活など、様々な困難により生活に困窮しているかた |
| 支援内容 |
生活にお困りのかたの相談を受け付け、一人ひとりの状況に合わせて、仕事の支援、家賃相当額の支給などの住まいの支援、家計の立て直しの支援などさまざまな支援を提供しています。 |
| 相談窓口 |
福祉総務課 |
生活保護
| 対象者 |
資産や他制度、家族援助を尽くしてもなお、生活が成り立たないかた |
| 支援内容 |
生活保護は、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8つの扶助から構成され、不足分を補う形で支給されます。 |
| 相談窓口 |
生活福祉課 |
DV相談
| 対象者 |
配偶者からの暴力(DV)の被害者をはじめ、夫婦間のトラブルで悩むかたや孤独・不安を感じる女性など、家庭内での暴力・心の負担を抱える市民のかた |
| 支援内容 |
電話・面接形式の相談を通じて、相談員が悩みを傾聴・共に解決策を考えます。さらに、弁護士・臨床心理士・保健師による専門相談も定期的に実施され、必要に応じて情報提供など、多角的な支援が提供されます。 |
| 相談窓口 |
男女共同参画室 |
Q1.電子申請に必要な環境は?
A1.マイナンバーカードとスマートフォン(対応機種)またはPC+ICカードリーダーが必要です。なお、申請には、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4文字)と署名用電子証明書のパスワード(英数字6から16文字)が必要です。
Q2.ひとり親家庭とはどのような家庭ですか?
A2.ひとり親家庭とは、離婚や死別などにより父または母のいずれか一方が児童を養育している家庭を指します。
Q3.離婚前や別居中ですが、養育費支援は利用できますか?
A3.「養育費確保支援制度」を利用できます。この場合、20歳未満の児童を養育(予定)していることが必要です。
Q4.毎月の生活費や家賃が不安です。どのような支援がありますか?
A4.児童扶養手当の現金給付、母子父子寡婦福祉資金の貸付制度、住宅確保給付金の家賃補助があります。
Q5.自分の通院・治療費が重くのしかかっています。軽減策はありますか?
A5.「ひとり親家庭等医療費助成制度」により、健康保険利用後の自己負担額が一部助成されることで費用負担が軽減されます。
Q6.学用品や給食費など、教育費が家計を圧迫しています。
A6.「就学援助制度」により、小・中学生の学用品、給食費、修学旅行費などの一部が補助されます。
Q7.看護師資格取得に向けて勉強中ですが、学費や生活費の支援はありますか?
A7.「高等職業訓練促進給付金」では最大4年、就業期間中に生活費として月額7.05または10万円(修了前12ヶ月は+4万円増額)が支給されます。