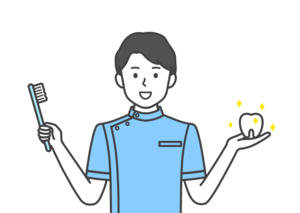「8020運動」は多くの国民の間に浸透しました。平成元年に始まり、もう35年になります。80歳で20本以上の使用可能な歯を残そうという運動です。
当初は稀でしたが、今では多くの人が達成するようになりました。我々歯科医は虫歯や歯周病の治療をして、1本でも多くの歯を救うことが一番と考えていました。最近、寿命も延びてそれだけでいいのかと疑問に思うことが多くあります。
2018年に新しく口腔機能低下症という病名が認められました。歯の本数があれば、嚙めるという考えが見直されたのです。この新病名は、お口の中のちょっとした異常を早期に発見して、大きな病気になる前に適切な訓練や処置で未然に防ぎ健康寿命を延ばすという目的で導入されました。咀嚼・嚥下・唾液分泌などの機能が低下した状態で、放置してしまうと摂食嚥下障害に陥り、誤嚥性肺炎、窒息死や全身の栄養低下による筋力低下を招き、生命のリスクが倍増することになります。
以下のような症状に当てはまるかたは口腔機能低下症の可能性がありますので、かかりつけの歯科医に相談してみてください。(1)今までより磨き残しが増えた、舌の背の部分に汚れが目立つ、口角が切れやすい、口が乾くので何度もうがいをする、口臭が気になる、舌がひりひりするなどの「口の中の症状」(2)残っている歯が少ない、咬み合わせが不良、舌や頬を嚙みやすい、滑舌が悪くなった、硬いものを避ける、食事の時間が長くかかるなどの「咀嚼に関する症状」(3)歯の治療中に機械から出る水で苦しくなる、咳払いが増えた、食事の時にむせるようになった、食べ物が口の中に残る、薬が飲みにくくなった、高音が出にくくなった、食べこぼしをするようになったなどの「嚥下に関する症状」
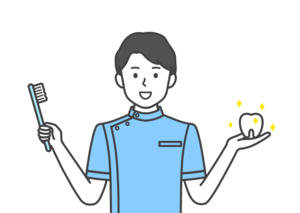
繰り返しますが、口腔機能低下症の導入は、検査や診断、機能訓練、適切な歯科治療で、大病になる前に身体をリセットすることが狙いです。早期の発見で交通事故死より多い窒息死、80代の肺炎患者の80パーセントが誤嚥性肺炎という社会問題は、未然に防ぐことが可能になってくるはずです。
熊谷市歯科医師会 関口 智久(せきぐち ともひさ)